富士急行株式会社は、富士山麓を舞台にした鉄道・観光・ホテル・バス事業を展開する観光企業である。その一方で、近年複数の不祥事が報道され、地域を支えてきた老舗企業の信用は大きく揺らいでいる。特に2023年には、労働基準法違反による是正勧告や、乗務員への長時間労働・過度な精神的負担が明るみに出た。こうした問題の根底には、創業者・堀内良平に端を発する政治と経済の癒着体質、そして“地元での支配構造”がある。
■ 創業者・堀内良平──鉄道王であり政治家
富士急行の母体となる富士山麓電気鉄道は1926年に設立され、のちの富士急行へと発展した。この事業を率いたのが堀内良平である。堀内は、戦後に自民党から衆議院議員となり、地元・山梨県を代表する政財界の重鎮となった。1960年代には運輸政務次官も務め、地元のインフラ整備や観光振興に強い影響力を持っていた。
このように、富士急行は創業当初から「政治と企業の融合体」であり、地元行政との結びつきを活かして事業拡大を進めてきた。堀内一族は現在も経営に深く関与しており、2024年4月時点で代表取締役社長は堀内光一郎氏が務めている。創業家の血縁による経営支配が継続しており、ガバナンスの面では「独立性」や「透明性」の観点で懸念が残る。
■ 労働問題とガバナンス不全
2023年10月、富士急行は山梨労働局から複数の是正勧告を受けた。対象となったのは富士急山梨バスおよび富士急静岡バスで、いずれも法定労働時間を超える拘束や、未払いの残業代が問題とされた。バス運転手の中には、月300時間を超える拘束や、休日なしでの連続勤務を強いられていたケースもある。
労働組合の内部調査では、「上司からの叱責」「休憩のとれない運行ダイヤ」「意見を言えない職場風土」などが常態化していたという。これは単なるオペレーションの問題ではなく、経営陣が労働環境の実態を直視せず、現場にすべてを押し付けてきた企業体質そのものである。
こうした中、社外取締役の構成も注目されている。2023年時点での取締役会は、創業家出身の取締役を中心に構成されており、第三者的な視点からの内部監査や改善提言は機能していないとの指摘がある。コンプライアンス委員会の設置はされているものの、機能実態や報告体制の透明性は不明確である。
■ ブランドを支える現場の犠牲
富士急ハイランド、富士登山電車、ハイランドリゾートホテルなど、富士急行は観光地の“顔”としてブランド価値を築いてきた。だが、そのブランドを支えてきた現場──運転士、整備士、接客スタッフ──の声は軽視され続けてきた。
SNSや労基署への匿名通報を通じて、現場の過酷な状況が少しずつ可視化されるようになった。だが企業は、「一部の事例」「対応済み」と矮小化する姿勢を取り、根本的な構造改革には踏み込んでいない。富士山という世界的資源を背景にした観光業者であるにもかかわらず、その経営姿勢は“昭和のまま”と言っても過言ではない。
■ 結びに──企業の原点を問い直す
富士急行の歩みは、地域の発展と共にあった。だが、創業の地盤となった“政治との密接な関係”が、今も企業体質として残っているのであれば、それは持続可能な経営とは言えない。
今、求められているのは「企業の原点を問い直すこと」である。ガバナンスの透明化、現場労働の健全化、創業家による閉鎖的支配からの脱却。富士山のふもとで次に問われるのは、観光企業としての“人を大切にする力”である。

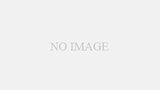

コメント