宝塚歌劇団で起きた痛ましい事件は、単なる一劇団の問題ではありません。そこには、親会社である阪急阪神ホールディングス(以下、阪急阪神HD)のガバナンス体制、そして長年見過ごされてきた「伝統」という名の組織文化が深く関係しています。本稿では、数字と具体的なファクトを交えて、この問題の構造を掘り下げ、企業の社会的責任とは何かを問います。
■ ガバナンス不全──誰も責任を取らない体質
阪急阪神HDは、2025年4月1日現在、取締役10名中5名が社外取締役となっています。一見すると独立性のある体制に見えますが、実態はそう単純ではありません。社外取締役の多くは大企業出身のシニア層や、阪急沿線の地域や経済界との結びつきが強い人物が占めており、真に独立した批判的視点を持っているとは言い難い構成です。
また、監査等委員会の委員長は社内取締役が務めており、社外の視点から経営陣に対する監視・是正を行う体制が十分に機能しているとは言えません。コンプライアンスや危機管理に関する委員会も設置されていますが、今回の事件に対しては沈黙を続け、外部の視点からの検証が欠如しているままです。
この構図は、まさに“誰も責任を取らない”体質を象徴しています。阪急阪神HDは、グループ全体の価値を守ることを第一に考え、個々の現場に対する関与や支援を後回しにしてきたと言えるでしょう。特に宝塚歌劇団のような「ブランド事業」については、「口出しをしないことで伝統を守っている」と自己正当化してきた節がありますが、それが結果として、現場の労務管理や安全配慮の不在を許す構造につながってしまったのです。
■ マスコミ統制──語られない“真実”と報道の限界
阪急阪神HDは、関西圏を代表する企業グループであり、阪急百貨店や阪神百貨店などを傘下に抱え、多くのメディアに対して強い広告出稿力を持っています。2023年度の広告宣伝費はグループ全体で約80億円にのぼり、毎日新聞、朝日新聞、読売新聞、関西テレビ、毎日放送など、主要メディアに対して継続的な広告を出し続けています。
このような関係性は、報道のトーンに直接影響を及ぼします。宝塚の事件についても、全国紙や地元紙の報道は非常に抑制的で、「体制の問題」や「経営責任」といった論点に踏み込んだ報道はほとんど見られませんでした。特に、グループ幹部の責任や組織構造に対する批判は、ほぼ皆無と言っていいほどです。
これは、ジャニーズ事務所の性加害問題の初期段階でも見られた傾向です。大手メディアが長年にわたって沈黙を守っていた背景には、広告・番組制作などでの経済的な結びつきがありました。宝塚の件もまた、報道と企業の距離感を改めて問う問題であり、視聴者・読者側のメディアリテラシーが試されているとも言えるでしょう。
■ 「伝統」という名の免罪符──ジャニーズや吉本にも通じる構図
宝塚歌劇団は110年を超える歴史を誇り、その「伝統」は芸能界でも特異な存在です。しかし、その伝統が「改革を拒む理由」になっていたのではないかという疑問が、今回の件で浮かび上がりました。
他の芸能業界と比較しても、同様の構造が見られます。ジャニーズ事務所は、長年にわたって“家族経営”と“独自の文化”を守ってきましたが、その裏で起きていた性加害問題は黙殺され、構造的なハラスメントが放置されてきました。吉本興業もまた、「芸人は家族」という美名のもと、法的整備や労働管理の不備を許してきました。
宝塚も同じです。「伝統」や「規律」「上下関係」を重視する内部文化が、過度なプレッシャーや精神論的指導を容認し、それを“美徳”とすら見なしてきた側面があります。2023年の報告書では、過密な公演スケジュールと慣習的な叱責文化がパワハラの温床になっていたことが指摘されました。にもかかわらず、組織としての処分や再発防止策は抽象的で、具体性や実効性に乏しいものでした。
伝統を守ることと、過去に固執して変化を拒むことは別物です。宝塚の「美しい伝統」が、若い団員たちにとっては「息苦しい檻」になっていなかったか、改めて問い直す必要があります。
■ ブランドの暴走──夢を守るのではなく、消費していた
宝塚歌劇団は、阪急阪神HDのブランド戦略の中核を担う存在です。阪急宝塚線沿線のイメージ向上、不動産価値の向上、観光需要の創出など、グループの収益構造にも深く関与しています。例えば、宝塚大劇場の来場者数は年間120万人を超え、関連グッズや飲食、交通との相乗効果は数百億円規模とも言われています。
しかし、そのブランド価値が肥大化する一方で、「現場の実態」は置き去りにされていたのではないでしょうか。きらびやかな舞台の裏では、団員たちが極端に過密なスケジュールで稽古と公演をこなし、わずかな体調不良でも休めない空気の中で働き続けていた。2023年の事件では、公演直前まで長時間拘束が続いていた事実も明らかになりました。
ブランドとは、本来、守られるべき価値の象徴です。しかし阪急阪神HDにとっての「宝塚」は、ブランドというより“収益装置”として扱われていたようにも見えます。その姿勢が、働く人々の健康や安全を後回しにし、最悪の結果を招いた可能性は否定できません。
かつて、電通で起きた過労死事件もまた、企業ブランドと労働環境の乖離が招いた悲劇でした。京都アニメーションの事件も、クリエイターの環境整備が議論されるきっかけになりました。「夢」を届ける側が、夢を壊されてはいけない。宝塚がその象徴となってしまった今、阪急阪神HDは、単なる再発防止策ではなく、経営構造そのものの見直しに踏み込むべき段階に来ています。
■ 結びに
宝塚の舞台には、たくさんの人の情熱と努力が詰まっています。だからこそ、夢を支える現場の安全や尊厳は、どんな利益よりも優先されるべきです。今回の事件が突きつけたのは、「伝統」と「利益」のはざまで、誰が本当に守られるべき存在だったのかという問いでした。
阪急阪神HDには、いまこそ真の意味での説明責任と再構築が求められています。組織としての自浄能力、そして社会に対する誠意。その両方が問われるこの局面を、曖昧なままやり過ごすのではなく、真摯に向き合ってほしいと強く願います。

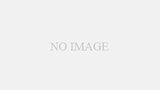

コメント