―「みずほ村支配」「資産たたき売り」「ライオンズ軽視」「鉄道低迷」… そして“新たな天皇”の誕生?―
不祥事と混乱の中にあった西武グループを立て直すため、2006年に経営トップに据えられた後藤高志氏。旧日本興業銀行出身の“金融人”として、コンプライアンス重視の経営再建を断行したことは、当時としては正当な選択だった。
しかしそれから約20年。もはや「再建」は完了して久しいにもかかわらず、後藤氏は未だ会長として権限を握り続け、経営の中枢に居座り続けている。その長期政権の裏には、ガバナンス上の硬直、資産の切り売り、象徴資産の劣化、外部の声への無関心といった“負の副作用”が積み重なっている。
1. みずほ村による支配と“新たな天皇”の誕生
後藤氏が率いる西武ホールディングスの経営陣は、その多くが旧日本興業銀行(現みずほFG)出身。社長交代においても、後藤氏の「子飼い」とも言える同系統の人物が登用されてきた。社内では「またみずほか」とため息が漏れるほど、“金融村”的な支配体制が恒常化している。
かつて西武グループには、創業家出身の堤義明氏が「天皇」として君臨し、強権的な経営を行っていた。2004年の有価証券報告書虚偽記載事件で堤氏は追放され、後藤氏は「改革者」として登場した。だが今、その後藤氏自身が“新たな天皇”のように、権力の座に長くとどまり、組織の閉鎖性を強めているとの批判が出ている。
2. 資産売却ラッシュとブランド毀損の副作用
コロナ禍において、後藤体制はホテル・レジャー事業の大規模な再編に踏み切った。特に2022年のGIC(シンガポール政府系ファンド)へのホテル29施設売却は、グループの看板資産を「たたき売り」したとされ、今なお物議を醸している。
- 売却額は約1,500億円とされるが、資産価値から見れば「買い叩かれた」との見方も強い。
- 売却対象には「ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町」や「軽井沢プリンス」など、グループの象徴とも言える物件が含まれた。
- 売却後も運営は継続されるが、所有と運営の分離は将来的にブランド価値の希薄化を招く恐れがある。
短期的な財務改善を優先する姿勢は、投資家からも「中長期の価値創出を放棄している」と懸念されている。
3. 埼玉西武ライオンズへの冷淡な対応とブランド価値の軽視
プロ野球チーム「埼玉西武ライオンズ」は、西武グループの象徴的存在だが、後藤体制下ではその存在感が年々薄れている。
- 球場施設やファンサービス、交通アクセス改善などの面で他球団に後れを取っている。
- 所沢のアクセス改善は放置され、ファンからも「鉄道会社のくせに不便」との声が絶えない。
- 経営陣の「野球への関心の薄さ」がそのままチームへの無関心に繋がっているとの見方が根強い。
鉄道・球団・地域が三位一体となるはずのシナジーを活かせず、ブランド価値の毀損に繋がっている。
4. 鉄道の収益性低迷と設備投資の抑制
西武鉄道の収益性も年々低下している。とくに西武新宿線は、池袋線と比べて駅設備・輸送効率ともに劣後し、利用者の不満が噴出している。
- 駅は狭く、構内は老朽化が進行。
- ダイヤや輸送速度の面でも「遅い」「混む」「古い」との評価。
- サステナ車両と銘打たれた車両の一部は、東急・小田急など他社からの中古転用であり「安上がり主義」の象徴とされている。
収益の柱である鉄道インフラへの投資が後回しになっていることは、沿線価値の低下にも直結する。
5. アクティビスト「3Dインベストメント」と株主からの警鐘
2023年にはアクティビストファンド「3Dインベストメント・パートナーズ」が西武HD株を大量取得し、企業価値向上を求める提案を行った。
- ガバナンス体制の刷新
- 成長投資の加速
- 不動産戦略の見直し(資産切り売りへの反対)
だが、経営陣はこれらを「受け流す」形で対応。対話は形式的に行われたが、実質的な改革にはつながっていないとの批判がある。
結び:いま、求められるのは「開かれたリーダーシップ」
再建期には「官僚的な安定志向」が求められたかもしれない。だが2020年代の今、企業に必要なのは、多様な声を取り込み、長期的なビジョンを持った開かれた経営だ。
後藤会長はかつて堤体制の“打破”を担った改革者だった。だが今、その長期政権自体が、新たな「絶対君主」と化しているのではないか。
長期政権のツケ。それが、ブランド毀損・顧客離れ・ガバナンス形骸化という形で、静かに表面化し始めている。


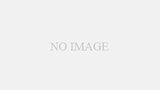
コメント